こんにちは、あめんぼです。
奈良検定2級、勉強方法で検索すると、
この方法で合格する、と多くの方が言われています。
実際はどうなのでしょうか?
結論からいうと、他でも言われているように、過去問を解くことで奈良検定2級は合格が狙えます。
しかし、勉強時間については10時間で足りないこともあります。
この記事では、
を、解説します。
なぜ、勉強時間が10時間以上必要か
奈良検定を受験される方は、
奈良が好き!奈良をもっとしりたい!視野を広めたい!といった方が多いと思います。
奈良検定の目的は、
になります。
奈良検定では毎年、「テーマ問題」の出題があり、それらに対する対策講座が開かれています。
検定を通して、奈良より深く知ってもらおうという意図が感じられますね。
奈良検定を受ける方も、共感するところがあると思います。
そのため奈良が好きな方ほど、過去問を解くだけでは収まらず、10時間以上の時間がかかることが想定されます。
私の場合は、過去問を元に学習ましたが、
など、をしていると第1回の過去問は最後まで解くだけで1時間半の時間がかかりました。
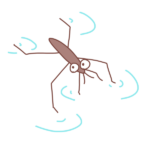
楽しくなると、その都度調べるので余計時間がかかります。
勉強方法として、実際に現地に行くこともありました。
実際、目で見て肌で感じることで記憶にも残ります。
なにより、奈良の思い出がふえると奈良がもっと好きになります。
結局、私の場合は、30時間程度勉強時間がかかりました。
しかし、余裕をもつことで知見が広がり楽しく学べたと思います。
奈良を知っていきたいと思う方ほど10時間以上、勉強時間を想定しておいた方が良いと思います。
勉強時間10時間以内で合格を目指す方法
とはいっても、
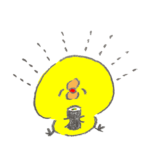
・時間がなくて、勉強に時間がさけない
・最低限の知識が欲しい
と、いった方もいらっしゃると思います。
ここからは、10時間以内で合格を目指す方法について解説します。
奈良検定2級合格のためには、以下の試験対策が必要です。
ですが、これら全てをやっていると10時間はゆうに超えてしまいます。
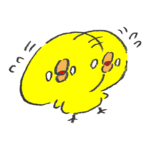
10時間以内におわらせたい!
といった方におすすめの勉強方法はこちらです。
です。
「暗記」が重要です。
検索や知識を広げると気付くと10時間をこえてしまいます。
これらには力はいれずひたすら過去問をとき解答を暗記します。
ここからは、「暗記」で合格可能な理由について解説します。
暗記で合格ができる
奈良検定は7~8割は過去問からの出題です。
過去問を解く回数をかさねると、同じ問題がでてくることに気付きます。
過去問第5回目くらいからは、同じ問題が多くなり、私の場合、第7回で正答率は6割、第10回では8割になりました。
第10回から先は、過去問からの出題が7~9割程度になります。
15回を2周程度で、合格基準である8割以上の正答率が目指せると思います。
過去問は慣れてくれば、1回5~10分程度で1回分(100問)解くことができます。
過去問おすすめのサイト
2024年12月現在、17回目までの過去問が公式サイトで確認できます。
時事ネタおすすめ勉強方法
ここまでで、過去問の周回で、8割以上の正答率が目指せることは、おわかりいただけたと思います。
次に気になるのが、「テーマ問題」と「時事ネタ」ではないでしょうか?
結論から言うと、「テーマ問題」も「時事ネタ」も対策は不要になります。
一般で行われているテーマ問題対策の講義の出席も不要です。
テーマ問題は、過去問からの出題もあり、新しい問題は5問、多くて8問程度です。
時事ネタも新しい出題は多くて5問程度です。
それ以外にも新しい問題はありますが、すべて間違えても8割程度は点数がとれます。
2周もすれば確実に合格は可能です。
それでも、
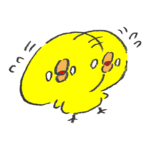
全く対策をしないのはちょっと不安だよ!
と、いった方もいらっしゃると思います。
大なり小なりお金を払って受験されるので、確実合格したい!と思われる方も多いと思います。
もし、短い時間で対策をするのであれば「テーマ問題」は公式ブック、「時事ネタ」は奈良ナビの聞き流しがおすすめです。
テーマに沿った部分を軽く読んでおきましょう。
「奈良ナビ」は奈良のニュースが凝縮されています。
聞き流しであれば時間はとらないですし、選択問題なので、頭に残っていれば解ける可能性があります。
まとめ
この記事では、奈良検定2級が本当に10時間で合格可能かを解説しました。
要点をまとめます。
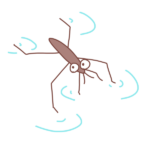
以上になります。
読んでいただきありがとうございました。
奈良通をめざしましょう!



コメント